
バリの風をお届け
バリコミュニケーション

バリ&インドネシアの小島から
バリ&ロンボク・リポート

南半球の楽園
クライストチャーチ・リポート
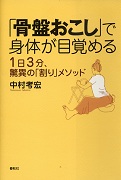
読んでみた本
「骨盤おこし」で身体が目覚める 一日3分、驚異の「割り」メソッド
|
りらいぶジャーナル
|
認知症 気持ち知れば変わる疑似体験でかかわり方知る 認知症の人とどう接すればいいのか――。その接し方を疑似体験しようと、リタイアメント情報センターでは11月、現場経験豊富な講師を招き、第4回シンポジウム「認知症なんてコワくない」を開催した。
「相手に心配していることを伝え、そして受け入れることが大事ですね」 否定・説得・責め・急かし禁物 寸劇では宮田さんから好評価を得たものの、現実生活ではそれが継続する可能性が高い。家族はいつまでも終わらない緊張と不安を抱えることになる。しかし、一人で抱え込まず専門家に相談したり、周囲に認知症の人を家族に持つ人がいたら声をかけたりするなど、今から意識することが大事なのだ。 宮田さんは認知症の人とのかかわりで重要なこととして、「否定しない」「説得しない」「責めない」「急がせない」と説く。そもそも「認知症の人」ととらえて身構えるのではなく、自然にさりげなくかかわることが大切だと話す。 「荷物は分かち合えば軽くなる。何がその人の力になり、何が力を削いでしまうのかを知ることです」 関連記事 ・気持ちがわかれば気づくことがたくさんあります R&I第4回シンポジウム 認知症ワークショップ |
自費出版図書館自費出版図書館では寄贈・新着図書を積極的に紹介します 記事インデックスリタイアメント情報センター |
|
|